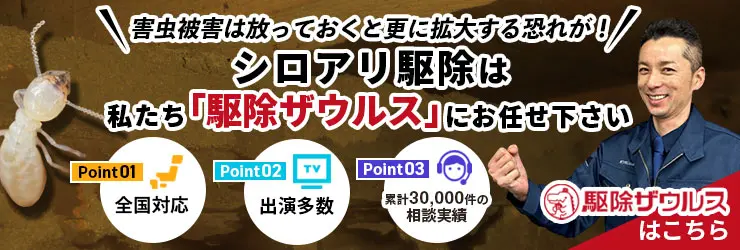シロアリの冬の生態を詳しく解説
シロアリの生態を知ることで、いつどのような対策を行うべきか理解することができます。大切な家を守るため、シロアリの生態について学んでいきましょう。

目次
シロアリの基本的な生態
シロアリは世界中に約3100種存在しますが、実際に建築物に被害を与える種は104種ほどです。
日本では20種類程度が生息していますが、中でもヤマトシロアリやイエシロアリなどの土壌性シロアリと、アメリカカンザイシロアリやダイコクシロアリなどの乾材シロアリの4種類が家屋にダメージを与える種として知られています。
家屋に対する脅威となる一方で、シロアリは自然界において重要な役割を果たしています。彼らは森林の枯死木や落ち葉を分解し土壌条件を改良する働きがあり、さらに干ばつ時の森林保護にも貢献しています。
建物には害を及ぼす存在として知られていますが、生態系の維持には欠かせない生き物なのです。
シロアリは冬どうしている?
シロアリの冬の生態ですが、おおむねどの種も低温には強くないため冬場の動きは鈍くなりますが、まったく活動しなくなるわけではありません。動きが活発な春から夏よりもペースは落ちますが、確実に木材を蝕んでいきます。
またシロアリの中でもヤマトシロアリの場合、10度程度の低温であれば活発な活動が可能なため、1年中変わらず増え続け食害を広げることになります。
それ以上温度が下がる場合、暖かい場所を求めて日当たりの良いコンクリートの下や温水器の近く、お風呂場の周りに移動するケースも見られます。
イエシロアリは巣の内部で温度を一定に保つ調整を行う習性があり、寒いときは壁を厚くして外気を遮断し、寒さをしのいでいます。
土壌性シロアリの特徴
土壌性シロアリの特徴は、地中深くに複雑な巣を形成し、湿度の高い土壌環境を特に好んで生活しています。
巣は通常、地表から30cm〜1m程度の深さに作られ、様々な大きさの部屋と通路で構成されています。これらのシロアリは主に地下から木材へと侵入を試み、適度な水分を含んだ木材を好んで摂食します。
またこの種のシロアリの特徴として、巣から餌場までの経路には蟻道と呼ばれる精巧なトンネルを築き上げ、その中を移動して体の乾燥を効果的に防ぐことが知られています。この蟻道は湿度と温度を一定に保つ機能的な役割も果たしています。
日本の住宅被害統計によると、このタイプのシロアリによる建築物への被害が圧倒的に多く、年間の被害報告件数の8割以上を占めています。
乾材シロアリの特徴
乾材シロアリは土壌性シロアリとは違い土壌との接触を必要とせず、乾燥した木材の中に直接巣を作って生活しています。
独特な生態を持つこのタイプのシロアリは、必要とする水分量が極めて少なく、一般的なシロアリが好む湿った環境がなくても生き延びられます。
そのため、建物の高層部でも容易に生息することができ、木材内部に小さな穴を徐々に開けながら、複雑な通路網を形成して生活圏を広げていきます。
このように乾材シロアリは木材内部で完結した生活を送るため、外部からの発見が困難であることが特徴的です。
主に外来種であるアメリカカンザイシロアリやダイコクシロアリがこれに該当し、温暖化の影響もあって冬の寒さが厳しい東北地方での被害が増加傾向にあり、建築物の保全における新たな課題となっています。
日本で猛威をふるうシロアリ4種
日本に生息するシロアリは20種を超えますが、家屋に巣食い被害をもたらす種類は以下の4種類です。それぞれの生態を見ていきましょう。
ヤマトシロアリの生態
ヤマトシロアリは土壌性シロアリとして知られ、地中深くに巣を形成し、特に湿度の高い環境を好んで生活します。
巣は複雑なつくりをしており、複数の機能を持った部屋と精巧な通路網を持った立体的な構造になっています。
蟻道と呼ばれる独特な通路システムは、巣から餌場までの移動経路として機能するだけでなく、体の乾燥を防ぐための湿度管理システムとしても重要な役割を果たしています。シロアリたちはこの保護された通路内を安全に往来しながら、効率的な採餌活動を展開しています。
この巣の中では、女王アリを頂点とする高度に組織化された階級社会が営まれており、各個体は明確な役割分担のもとで協力して生活しています。
ヤマトシロアリの特徴
| 体長 | 働きアリ: 4〜5mm、兵アリ: 5〜6mm |
| 巣のサイズ | 数千〜数万個体 |
| 生息地 | 冬の寒さにも強く、日本全土(北海道南部から沖縄まで)に広く分布 |
| 巣の特徴 | ・地下30cm〜1m程度の深さ ・複数の部屋と通路で構成 ・土壌中に蟻道を形成 |
| 被害の特徴 | ・湿った木材を好んで食害 ・日本の木造建築被害の9割以上を占める ・徐々に進行する継続的な被害 |
イエシロアリの生態
土壌性シロアリの一種、イエシロアリの体長は他の種と比べて大きく、働きアリで体長4〜5mm、兵アリで6〜7mmです。
主に南日本の温暖な地域に生息し冬は比較的苦手ながらも、年平均気温が20度以上の高温多湿な環境を特に好んで生活します。巣は地中の深い場所に作られ、通常は地下1〜2メートルの深さに及ぶ複雑な構造を持ち、複数の女王が存在する場合もあります。
イエシロアリの特徴的な点として、巣の中には数十から数百の部屋をつくり、それぞれが育児室や貯蔵室などの特定の機能を持っています。
建築物への被害も極めて深刻で、一度侵入されると短期間で大規模な食害を引き起こす可能性があります。1年以内に柱や梁に重大な構造的損傷をもたらすことも珍しくありません。
イエシロアリの特徴
| 体長 | 働きアリ: 4〜5mm、兵アリ: 6〜7mm |
| 巣のサイズ | 最大で数百万個体 |
| 生息地 | 南日本の温暖な地域(年平均気温20度以上の高温多湿な環境) |
| 巣の特徴 | ・地下1〜2メートルの深さ ・数十から数百の機能的な部屋(育児室、貯蔵室など) ・複数の女王が存在する場合あり |
| 被害の特徴 | ・短期間で大規模な食害 ・1年以内に柱や梁に重大な構造的損傷をもたらす可能性 |
アメリカカンザイシロアリの生態
アメリカカンザイシロアリの生態は乾材シロアリの代表的な種として広く知られており、その特異な生活様式は研究者の間でも注目を集めています。
他のシロアリ種と異なり、土壌との接触を全く必要とせず、乾燥した木材内に直接巣を形成して生活することが最大の特徴です。
体長に関しては、働きアリが約4mm、兵アリが約5mmとコンパクトなサイズであり、1つの巣のコロニーサイズも先ほど紹介したヤマトシロアリとイエシロアリよりも小さいです。
アメリカカンザイシロアリは建物の高い所でも容易に生息が可能で、木材内部に精密な穴を徐々に開けながら、巧みに生活圏を拡大していきます。
木材表面に直径2mm程度の小さな穴を規則的に開け、内部を不規則かつ複雑に食害していく点、木材を消化した後の糞(フラス)を穴から定期的に排出する点が特徴的で、この排出物の存在が被害発見における重要な手がかりとなっています。
土壌性シロアリとは違い蟻道を作らないため、外部から発見しづらいという特徴もあり、駆除業者も苦戦を強いられるタイプのシロアリです。
以前は関西以南に見られていましたが、近年では地球温暖化の影響によって生息可能域が着実に北上しており、日本国内での分布域が徐々に拡大していることが専門家によって確認されています。日本の冬の寒さにも適応している種類です。
アメリカカンザイシロアリの特徴
| 体長 | 働きアリ: 約4mm、兵アリ: 約5mm |
| 巣のサイズ | 数千個体程度 |
| 生息地 | 木材内部に直接営巣(土壌との接触不要) |
| 巣の特徴 | ・乾燥した木材内に直接巣を形成 ・木材内部に精密な穴を開けて生活 ・直径2mm程度の小さな穴を規則的に開ける |
| 被害の特徴 | ・木材内部を不規則かつ複雑に食害 ・フラス(糞)を穴から定期的に排出 ・建物の高層部でも被害が発生 |
ダイコクシロアリの生態
ダイコクシロアリは主に亜熱帯地域に生息し、他の日本のシロアリと比べて体が大きく、働きアリで6〜7mm、兵アリで8〜9mmにも達します。体の大きさを活かして、強力な顎で木材を効率的に切断し、巣の拡大や採餌活動を行います。
完全に木材内部に巣を作り、土壌との接触を必要としないため、建物の上層階でも生息が可能です。ほかのシロアリと同じくその巣は複雑な構造を持ち、育児室や貯蔵室など、機能に応じて異なる部屋を持っています。
湿度管理能力が高く、乾燥に強い特性を持ち、一度侵入すると大規模な被害をもたらす可能性があります。木材内部を速いスピードで食害し、短期間のうちに建築物の構造を著しく損なうことがあります。また、巣が発見されにくい場所に形成されることも多く、被害が発見された時には既に深刻な状態になっていることも少なくありません。
ダイコクシロアリの特徴
| 体長 | 働きアリ: 6〜7mm、兵アリ: 8〜9mm |
| 巣のサイズ | 比較的小規模なコロニー |
| 生息地 | 亜熱帯地域、木材内部に直接営巣 |
| 巣の特徴 | ・木材内部に複雑な構造を形成・育児室や貯蔵室など機能別の部屋を持つ・独自の湿度管理システムを持つ |
| 被害の特徴 | ・木材を速いスピードで食害・建物の上層階でも被害が発生・発見が困難で被害が深刻化しやすい |
シロアリの生態と階級
シロアリの生態として非常に特徴的なものがあります。それは階級です。
以下のような階級に分かれ、それぞれ別の役割を持ちながら巣を拡大し、その数を増やしていきます。
シロアリの階級は主に以下の4つに分かれています。
- 女王・王(生殖虫)
- コロニーの創設と繁殖を主な役割とし、新しい巣の形成を担当。巣の立地場所の選定から、最初の働きアリの育成まで、コロニーの基礎作りの重要な過程を管理する
- 一日に数千個もの卵を産み続け、巣全体の個体数を維持・増加させるとともに、フェロモンを分泌してコロニーの社会構造を制御。このフェロモンは各個体の行動や発達を調整し、効率的な分業体制を確立する上で重要な役割を果たす
- 職蟻(働きアリ)
- 木材をかじって巣の通路を作り、巣内の温度や湿度を調整し、壁や天井の補修も行う
- 幼虫の世話や餌の確保を担当。女王の身体を舐めてケアを行う個体などもいる
- 兵蟻(兵アリ)
- 巣の防衛を担当する個体で、頭の形が働きアリとは異なる
- 外敵から巣を守る役割があり、侵入した昆虫などに対して攻撃を加える
- 幼虫
- 卵から孵った個体で女王アリの周辺で働きアリが運んできた栄養を食べて育つ。孵化したばかりは透明な色をしているが、木材を消化するようになると乳白色へと変化。成長して各階級に分化する
乾材シロアリの「擬職蟻」
乾材シロアリには、擬職蟻(ぎしょくぎ)が存在します。
通常のシロアリの場合、職蟻から兵蟻やニンフ(羽アリや副王・副女王になる前の幼虫)への分化、そしてニンフから羽アリ(新女王・新王)への分化という固定的な発達経路が存在します。
一方で、乾材シロアリの擬職蟻は、この一般的な発達経路にとらわれない柔軟性を持ち、状況に応じて全ての形態へと分化できる特殊な能力を備えています。
他のシロアリでは、コロニーが大きな被害を受けて職蟻だけが生き残った場合、新しい王や女王を生み出すことができないため、必然的に巣は衰退へと向かいます。
例えばヤマトシロアリの場合、25匹もの個体が生存していても、コロニーの再生はほぼ不可能です。これは主に、王の代替となる個体が発生する可能性が著しく低いことに起因しています。
これに対して、擬職蟻は少数の個体でも副生殖虫(副女王・副王)へと分化する能力を持っており、巣が危機的状況に陥った場合でも、効率的にコロニーを再構築することが可能です。
この適応能力は、長い進化の過程で獲得された生存戦略として非常に重要な意味を持っており、種の存続に大きく貢献する特殊能力だと考えられています。
この擬職蟻を持つアメリカカンザイシロアリは、被害件数は少ないものの潜在的な脅威が大きいことがわかります。
シロアリはなぜ木材を消化できるのか?消化生理を解説

シロアリの不思議な生態としてその食性があげられます。そもそもシロアリはなぜ木材を食糧にしているのでしょうか。
その理由は、シロアリの消化システムの中核となる腸内に共生する原生生物(原虫)とバクテリアの特殊な働きにあります。
これらの微生物は、何百万年もの進化の過程で高度に進化した共生関係を築いており、木材の主成分であるセルロースを非常に効率的に分解する能力を獲得しています。
分解されたセルロースは、シロアリの体内で吸収可能な単純な糖類や様々な栄養素へと変換され、エネルギー源として利用されます。
このプロセスは非常に精巧で、木材のほぼすべての成分を無駄なく活用することができます。
実はもともとシロアリ自身は木材を消化する酵素を持っていなかったものの、数百万年という長い進化の過程で、この微生物との緊密な共生関係を確立してきたと考えられています。
この独特な消化システムによって、他の昆虫では全く利用できない木材を主食として効率的に生活することが可能となり、生態系の中で独自の地位を確立しています。
この共生関係は非常に緊密で、シロアリが新しい巣を作る際には、これらの微生物も確実に次世代に引き継がれるような精巧な仕組みが発達しています。
特に若いシロアリは、巣の中の成熟した個体から直接的な接触を通じて、微生物を受け継ぐことができます。
まとめ
シロアリの生態について解説してきました。
彼らは種類ごとに高度な階級社会を形成してその生息範囲を拡大し、人間の生活範囲で行うことによって家屋に大きな損傷をもたらします。
種類によっては冬の寒さも問題なく活動するため、大きな被害が出る前に対策をとっておかなければなりません。
シロアリ調査、駆除のお見積りは駆除ザウルスへお気軽にご相談ください。