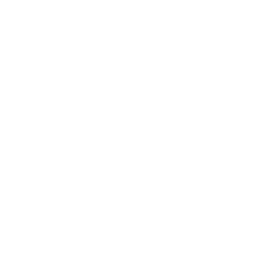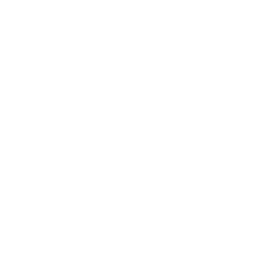アナグマの生態と被害について
日本に多くいるアナグマ(穴熊)は「ニホンアナグマ」という在来種のことを指し本州・四国・九州・小豆島の地域で生息が確認できています。 主に夜間に活動しており、ネズミやウサギ、ミミズや昆虫類、鳥などのほか、果実や木の根、木の実、穀類などを好む雑食の害獣です。 警戒心は強くなく人間が近づいても逃げない傾向にあります。九州地方の方はよくアナグマを見かけることが多いのではないでしょうか。 床下などに棲みついてしまうと厄介な害獣のため早急な駆除対策をおすすめします。
アナグマの生態

| 体長 | 40~70cm 目の周りは黒く、鼻~後頭部にかけ顔の中央部に明るい色の帯が一本あります |
|---|---|
| 体重 | 10~13kgが一般的 手足が短く寸胴体系 |
| 体色 | 基本的に薄い茶色のものが多いですが、汚れのために真っ黒く見えるものも多くいます。 |

 <長くするどい爪を持ったアナグマ>
<長くするどい爪を持ったアナグマ>
成獣(大人になった害獣)となった場合の足跡の大きさは6cm程度です。巣穴を掘るアナグマは、長くするどい爪(鉤爪)を持っています。

アナグマの糞はハクビシンと似ている傾向にあり、理由として食べる物が似ているからと言われています。一番の違いは穴を掘って糞をすることです。具体的に説明すると以下が挙げられます。
- (1)浅く穴を掘って糞をする
- (2)糞の表面に光沢、テカリがある
- (3)糞を崩すと半分以上が土や泥っぽい
アナグマの特徴
アナグマ(穴熊)は名前の由来の通り、穴を掘るのが得意でそこに巣穴を作り生活しています。 平均気温が10℃以上になる活動が盛んになり、11月下旬~4月の暖かくなる季節まで冬眠しています。 九州では冬季に捕獲されている例もあるので穴にこもっていない個体もあると考えられています。 出産は春に行われ4月頃がピークとなります。一度の出産で1頭~4頭の子を生みます。 母子を中心とした6~7頭の集団で生活しており、単独で生活する雄が巣穴、餌場を共有する習性があります。 巣穴の暮らしをメインとし手足は短く耳などのでっぱりも小さくなっています。寸胴体型ですが、木登りも得意。 日中に寝る際には、地面ではなく木の上で休むことも多いと言われてます。
アナグマの主な特徴
- アナグマは在来種で本州・四国・九州・小豆島の地域で生息
- 夜行性
- ネズミやウサギ、果実や木の実などを好む雑食の害獣
- 性格は温厚で人間が近づいても逃げない傾向
- 手足が短く寸胴体系
- 長くするどい爪(鉤爪)がある
- 糞は光沢があり浅く穴を掘って糞をする
アナグマの被害
アナグマの食生は雑食のため、様々な農作物を荒らす被害が報告されています。また、私達の住まいにも被害を与える害獣であり、いくつかご紹介させていただきます。
 <床下柱部分に巣穴を作ったアナグマ>
<床下柱部分に巣穴を作ったアナグマ>
建物の下(床下)に巣穴を作られ地盤が緩くなり構造上の欠陥が発生するなどして、経済的被害が起きる可能性があります。
 <拡張されたアナグマの巣穴>
<拡張されたアナグマの巣穴>
巣は毎年拡張され、深さ4m以上になることもあります。巣は親子で受け継ぐ習性があり、幼獣から成獣までたくさん生活しています。
 <ため糞をするアナグマ>
<ため糞をするアナグマ>
タヌキほどではありませんがアナグマもため糞をする習性があります。放置すると糞は溜まり続け、衛生的にあまりよろしくはありません。
アナグマによる主な被害
- 建物劣化による経済的被害
- 排泄物による衛生的被害
- 侵入被害
- 異臭被害
- 農作物を荒らす被害

お客様のほとんどが初めての害獣駆除。些細なことでもけっこうです。まずはご相談ください!

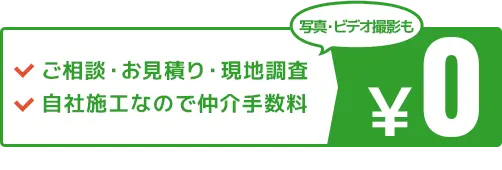

電話、メール、LINEのいずれか得意な方法をご選択いただけます
- 電話で話したい(通話無料)
- 電話がつながりやすくなっております
- メールで話したい
- お見積・現地調査 0円
- 被害・施工の画像データお渡し
対応エリア
- 東北・関東・東海・北陸・近畿・中国・九州(一部地域除く)