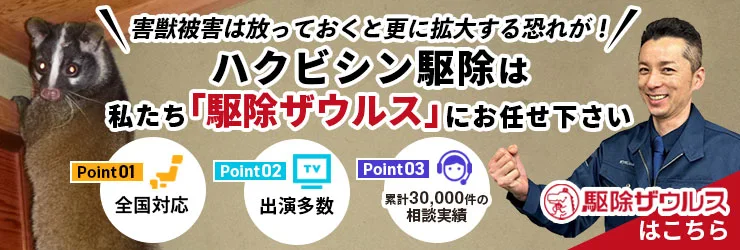ハクビシンのフンってどんな形?特徴や処理方法、対策を紹介

ハクビシンは一見可愛らしい外見ですが、れっきとした害獣の一種です。
「近隣でハクビシンの目撃情報があった」「ハクビシンの被害を受けた家がある」などの噂を耳にして気になっているという方も多いのではないでしょうか。
この記事ではハクビシンのフンを判別する方法や特長、処理方法について解説しています。
目次
ハクビシンとはどんな生き物?
ハクビシンは東南アジアから台湾、インド、スマトラなどの広範囲に分布しているジャコウネコ科の動物です。
日本でも昭和20年代から生息分布域を拡大しており、現在では大阪府と鳥取県、大分県、沖縄県を除いた43都道府県に分布しています。
体長はしっぽ込みで約90〜110cm、体重は約3〜4kgと小型犬や猫よりやや大きいです。
全身が灰褐色で「白鼻芯(ハクビシン)」の名の通り、額から鼻先まで白い模様があります。
完全な夜行性で、木登りが得意で樹洞や人家の屋根裏に住み着くケースが多くみられます。
行動範囲は約70ヘクタール程度と身体のわりにかなり広く、オスの方がより広い範囲で行動する傾向があります。
果実を特に好みますが基本的には雑食で、サクランボやリンゴのような果樹や家庭菜園を喰い荒らすことも少なくありません。
バランス感覚が非常に優れており、電線の上を移動して庭先に侵入してくることもありますが、ネズミやアナグマのように穴を掘ることはないようです。
ハクビシンのフンを判別する3つのポイント
ハクビシンが侵入しているかを知るポイントとして、フンの有無が挙げられます。ハクビシンのフンには、どのような特徴があるのでしょうか?
ここではハクビシンのフンの形や大きさ、ニオイなど、のポイントを3つご紹介します。
| 形 | ハクビシンのフンは丸く細長い形をしており、黒褐色や茶色をしています。果実や野菜を好んで食べるので、種や野菜カスのようなものが混ざっているという特徴もあります。 |
| 大きさ | 大きさは5cm〜15cm程度で、あまり大きくありません。食べているものや環境によって多少サイズは異なりますが、小型犬や猫のフンと同じくらいの大きさと考えれば良いでしょう。 |
| ニオイ | ハクビシンは果物を好んで食べることもあり、フンのニオイはあまり強くありません。フンをした直後は甘い匂いになることも。しかしジャコウネコ科の動物だけあって、尿のニオイは強烈です。 フンと尿を一か所でするので、尿の悪臭が発見のきっかけになることもあります。 |
尿やフンを一か所でする習性がある
ハクビシンには、決まった場所でフンや尿をする「ためフン」と呼ばれる習性があります。
ねぐらの周辺ですることが多いため、屋根裏に住み着いている場合は大量のフンや尿が天井裏を圧迫して歪んだり、シミができることも。この段階になって、初めてハクビシンの存在に気付くケースもみられます。
他の動物のフンと違いはある?
ハクビシンと間違えられやすい害獣として、タヌキやアライグマ、などが挙げられます。
タヌキのフンは黒く丸く、大きさは2~3cm程度と小さめ。ハクビシンと同じくためフンの習性がありますが、ニオイはタヌキのほうがはるかに強いです。
アライグマのフンは5~20cm程度で、形は一定していません。アライグマは雑食性のため、フンには鳥の羽や動物の骨などが混ざっています。こちらもニオイはかなり強烈です。
イタチのフンは6mm程度とかなり小さめですが、水分を多く含んでいるので重みがあるのが特徴です。イタチはスカンクの仲間なので、硫黄のような強烈なニオイのフンをします。
ハクビシンと他の動物のフンを見分けるには、大きさやニオイの有無がポイントになるといえそうですね。
ハクビシンのフン害が起きやすい場所とは

近年、ハクビシンは住宅地にも多く生息していることが分かっています。当社に寄せられるご依頼のなかにも、家のなかにハクビシンが住み着いてしまったというものが少なくありません。
ここでは、ハクビシンのフン害が起きやすい場所や、被害の兆候について解説しています。
本来は森林に生息していた
ハクビシンは本来、森林に生息する動物です。自分で巣を作ることはなく、タヌキやアナグマの古巣や木の穴、洞窟のような場所をねぐらにしていました。
しかし、生息環境の減少などにより住宅地に出てくるようになってからは、民家の屋根裏や床下を巣にするケースが多くみられます。
ハクビシンのフンが見つかりやすい場所
屋根裏は人気がなく暗く、静かで暑さ寒さをしのぎやすいため、ハクビシンにとって非常に都合の良い場所です。ハクビシンが巣を作っているサインとして、以下のようなものが挙げられます。
・天井や床下で何かが走っているような足音がする
・天井の隅にシミが広がっていたり、板がゆがんでいる
・農作物(特に果樹)の食害が出ている
このような兆候がある場合、近くにハクビシンの寝ぐらがある可能性が高いです。さらに以下のような場所は、ハクビシンのフンが発見されやすい場所です。
・屋根裏
・床下
・人の出入りが少ない納屋や倉庫
・屋根の上
・庭の隅
ハクビシンには、寝ぐらの周辺など特定の場所でフンや尿をする「ためフン」の習性があります。こういった場所でフンを見かけたら、その周辺に寝ぐらがあると思って間違いないでしょう。
ハクビシンを放置することで起きる3つのデメリット
ハクビシンによる被害を放置していると、さまざまなデメリットが生じます。ここでは特に大きなデメリットを3つご紹介しています。
家屋がダメージを受ける
ハクビシンは一か所に集中してフンや尿をするため、その周囲に甚大なダメージを与えます。天井裏が重みでゆがんだり、断熱材や梁に尿がしみこんで腐食してしまったりすると、駆除だけでなく大規模なリフォームが必要になることも。
ハクビシンのフンは害獣のなかでは比較的ニオイが弱いほうですが、ニオイのきつい尿と混ざると強烈な悪臭になります。
また、配線をかじられたり、フン尿をかけられるなどで配線がショートすると、火災の原因にもなります。実際に害獣が原因で起きる火災も少なくありませんが、これらは保険の対象外になることもあるのです。
感染症や害虫を媒介する
ハクビシンの身体にはノミやダニが寄生しています。ノミやダニは畳の目や家具のすき間などから室内に侵入し、アレルギーや喘息、皮膚疾患を引き起こす要因になります。
また、フンにカビが生えると、有害な胞子が家中にまき散らされてしまいます。こちらも健康に多大な影響を与える要因のひとつです。
特にご高齢の方や基礎疾患のある方は、重症化すると命にかかわる事態に発展することもあるので早急な対応が必要です。
さらに深刻な健康被害を及ぼす可能性があるのが、ヒゼンダニが媒介する疥癬症です。角質層にダニが潜り込んで皮膚疾患や強いかゆみを引き起こす疥癬は、老人ホームや病院で大変恐れられている感染症のひとつです。
一度感染すると家族や職場にまで広がってしまうだけでなく、ペットにも感染する可能性があります。
ハクビシンの本体やフンが媒介する感染症は、メカニズムが解明されていないものも含めて多数あります。被害が起きる前にしっかりと対策を取ることが大切です。
農作物が被害を受ける
ハクビシンは果実を好んで食べる性質があるため、畑や果樹園が食害に遭うことがあります。
高いところを移動するのが得意なので、柿やみかんなど樹上に生る果実の被害が多い場合は、ハクビシンによるものと考えたほうが良いでしょう。
ハクビシンの行動半径は約70ヘクタールにも及ぶといわれています。自宅に居着いたハクビシンを放置していると、近隣にも多大な被害を及ぼす可能性があるので注意しましょう。
ハクビシンのフン処理、自分でやることは可能?
ハクビシンのフンがどこにあるか判明している場合や、被害が甚大で急を要する場合、なんとか自分たちで処理できないかとお考えの方もおられると思います。
ここではすぐに実行できるハクビシンのフン処理方法と追い出す手段についてご紹介します。
徹底した防護が大切
先にも解説したように、ハクビシンのフンはさまざまな病原体を媒介する汚染物質です。近づく場合は、必ず厳重な防護体制を取らなくてはいけません。
・肌をすべて覆う丈夫な服
・粉じんを防ぐ防護ゴーグル
・分厚い手袋
・口周りをすべて覆う防塵マスク
こういった装備を用意してから処理に臨みましょう。
フンを取りのぞく時は粉じんが舞わないように作業して、汚染をできる限り広げないようにする工夫が必要です。
また、掃除に使用したほうきやチリトリには、病原体が多数付着している可能性があります。
使い捨てにするか、使用後はしっかり洗浄・消毒しておくようにしましょう。
家庭でできる追い出し手段
フンを取りのぞいたあと、考えなくてはいけないのが再侵入を防ぐ手段です。ただフンを掃除しただけでは、またハクビシンに侵入されて巣にされてしまいます。
家庭でできる追い出し手段として、忌避剤やくん煙剤を使う方法が挙げられます。これらはハクビシンの嫌うニオイや成分を発するもので、ホームセンターなどで手軽に購入できます。
それなりの効果が期待できますが、ハクビシンがニオイや成分に慣れてくると効果が落ちるという点と、他のペットや家畜に影響が出やすいというデメリットがあります。
ハクビシンの駆除をプロに依頼する3つのメリット
自分たちでハクビシンを駆除する方法について解説してきましたが、実際にやってみるとかなり困難を伴う作業である感じた方も多いのではないでしょうか?
プロの害獣駆除業者は培った多くの業務経験とプロ仕様の機材を用いて、速やかにハクビシンによる被害を復旧し、再侵入を防ぐ策を講じます。
ここでは、具体的なメリットを3つにまとめました。
効率性とスピード感
プロの害獣対策業者は害獣駆除に関する豊富な業務経験と専門知識を蓄積しています。
ハクビシンの習性についても熟知しているので、姿が確認できていないケースでも迅速に移動ルートや巣を特定し、駆除へと移行することが可能です。
高い安全性
害獣駆除に使用する機材や薬剤は、正しい知識とノウハウによって運用されています。これにより高い効果を出すだけでなく、人間やペット、周辺環境への影響を最小限に抑えることが可能です。
また、感染症や病原菌に対する防護にも細心の注意を払い、安全に作業を進めていくのが特徴です。
法令の遵守
ハクビシンをはじめとする害獣駆除は、家から追い出して住宅地や畑に近づけないのが基本です。害獣の捕獲には地方自治体の許可が必要なことと、たとえ捕獲しても周辺で別個体が生息していたら同じことの繰り返しになってしまうからです。
プロの害獣駆除業者は個々のケースに応じて、法令を遵守しながら最適な駆除方法を選択するノウハウを有しています。
駆除ザウルスでは業務経験豊富なスタッフが各地の営業所から迅速に駆けつけ、無料でお見積りを作成いたします。
他者ご利用後の再発被害にも対応しておりますので、しつこく続くハクビシンの被害にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
害獣のお悩みや駆除のご相談は全国対応の「駆除ザウルス」へ!【見積もり・現地調査無料】